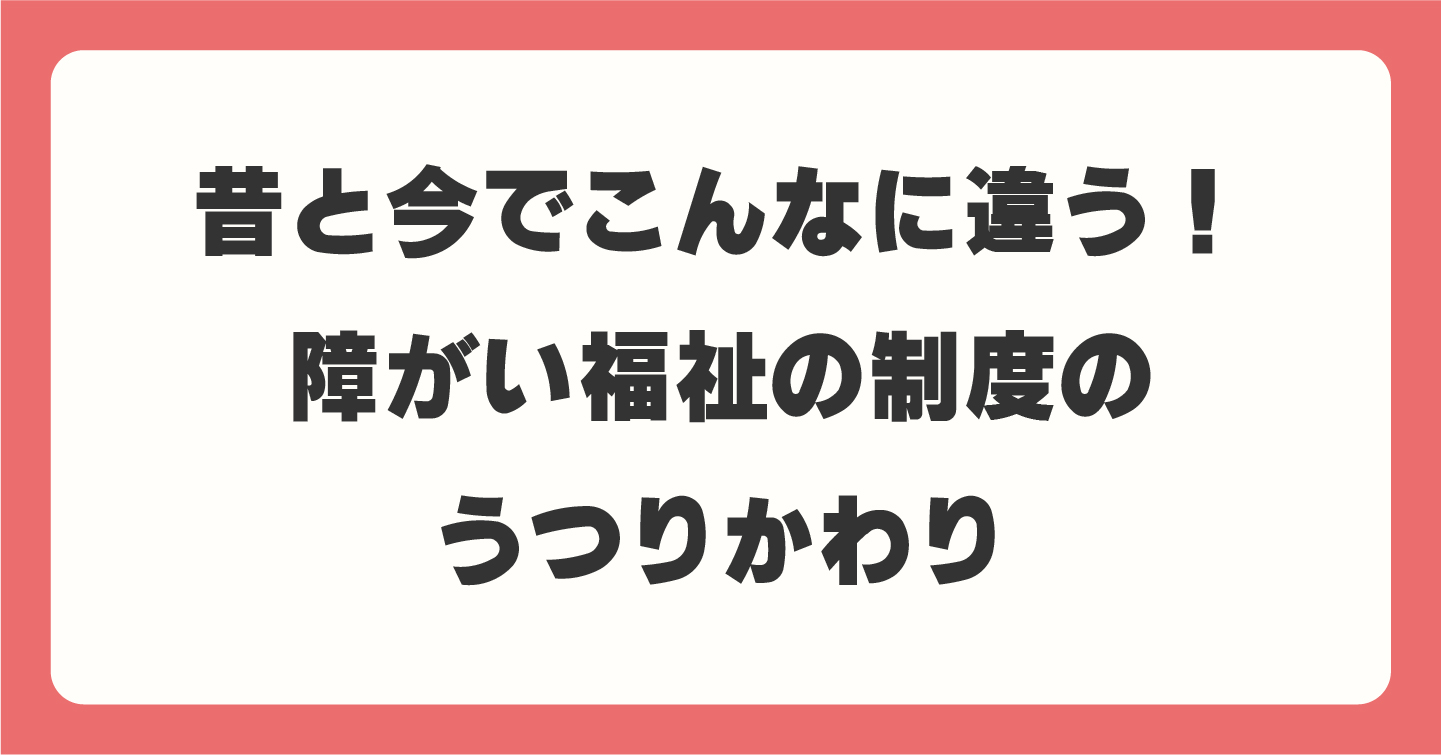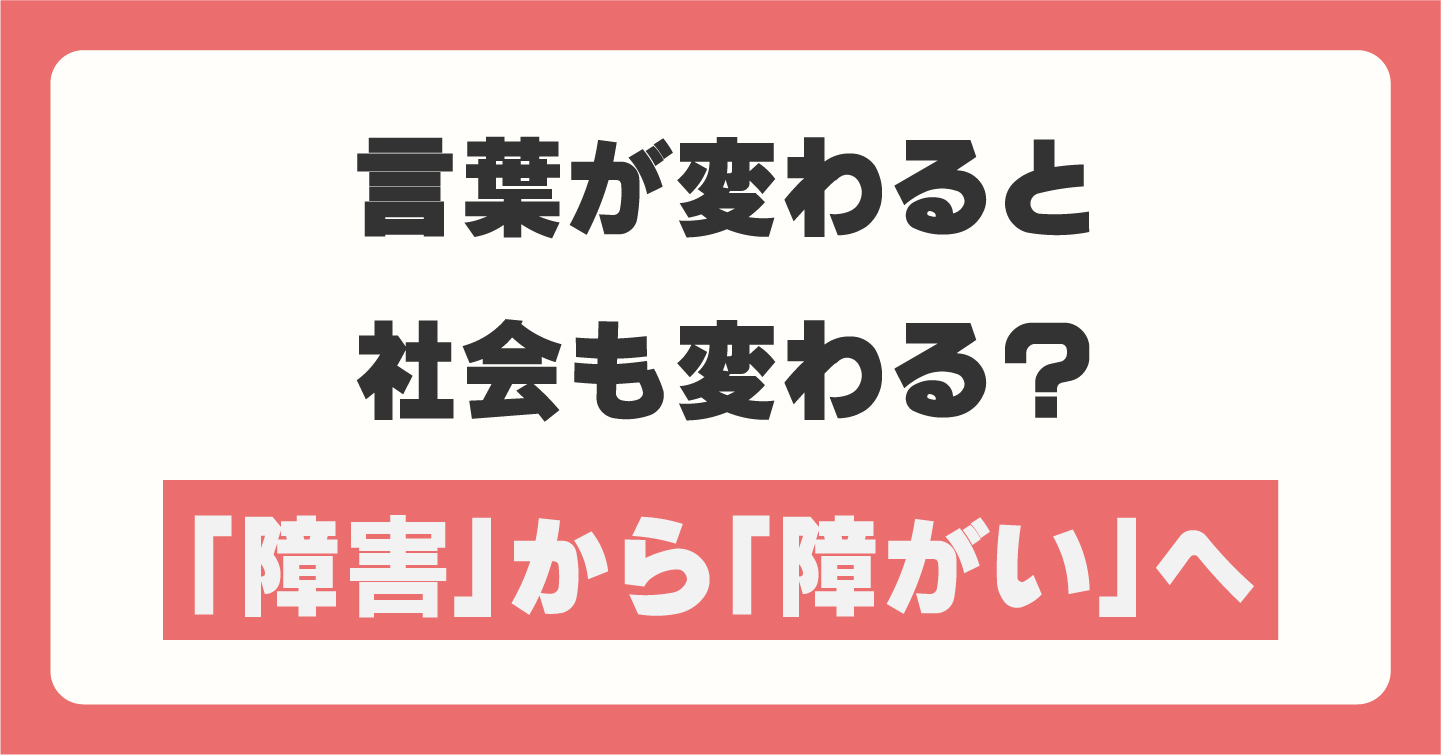日本における障がい福祉制度は、戦後から今日に至るまで大きな変化を遂げてきました。かつては「保護」の色合いが強く、障がいのある人を社会から隔離するような仕組みも存在していました。しかし、時代の流れとともに「共生社会」の理念が広がり、今では地域で暮らしながら必要な支援を受けることができる制度へと発展しています。本記事では、障がい福祉制度の歴史を振り返りながら、昔と今の違いをわかりやすく解説します。
戦後から高度経済成長期の障がい福祉
施設中心の支援と「保護」の時代
戦後間もない頃の障がい福祉は、生活困窮者への援助と同じく「福祉国家の保護」という色合いが強くありました。障がいのある人は地域での暮らしよりも施設での生活が中心であり、就労や社会参加の機会は限られていました。1950年に制定された「身体障害者福祉法」は、義手や義足の交付、就労指導などを目的としていましたが、基本的には“社会から隔離する”仕組みが前提となっていました。
「施設入所」が当たり前だった背景
この時代は障がいを「医療・保護の対象」とみなし、社会の一員としての参加よりも、安全に管理することが重視されていました。経済成長の恩恵が行き渡らず、福祉予算も限られていたため、社会資源は十分に整っていなかったのです。
1970年代~90年代の制度拡充
「自立」への道筋と在宅福祉の始まり
1970年代以降、障がい者運動の高まりや国際的な人権思想の影響により、障がい者福祉は「保護」から「自立支援」へと方向転換を始めます。1973年の「心身障害者対策基本法」改正では、雇用促進や生活支援の観点が盛り込まれました。さらに1981年の「国際障害者年」を契機に、在宅で暮らす障がい者を支援する制度が整備されていきました。
ホームヘルプやデイサービスの普及
この頃から「施設に入らず地域で生活する」という考え方が広まり、ホームヘルプ(訪問介護)やデイサービス(通所サービス)が各地で導入されました。障がい者本人が「選んで生活する」という視点が芽生えたことが、この時代の大きな特徴です。
2000年代の転換点—自立支援法の成立
「応益負担」という新しい考え方
2006年に施行された「障害者自立支援法」は、現代の制度への大きな転換点でした。サービスを利用する際、利用者が一律1割を自己負担する「応益負担(サービスを利用した分だけ負担する仕組み)」が導入されました。これは“支援は権利”という発想を強調する一方で、負担の重さから批判も多く、後に見直されることになります。
サービス体系の一元化
また、それまで「身体障害」「知的障害」「精神障害」と分かれていたサービス体系が一本化され、障がい種別にかかわらず共通の仕組みでサービスを受けられるようになった点は、大きな前進でした。
現在の制度—共生社会への歩み
障害者総合支援法と合理的配慮
2013年には「障害者総合支援法」が施行され、「障害者自立支援法」を引き継ぎつつも利用者の自己負担軽減策が導入されました。また、2016年には「障害者差別解消法」が施行され、学校や職場などで「合理的配慮(障がいのある人が他の人と平等に参加できるよう環境や対応を調整すること)」が義務化されました。
地域生活を支える制度へ
現代の制度は、入所施設ではなく地域での生活を基本とし、就労支援、相談支援、地域生活支援事業など多岐にわたる仕組みで支えています。かつては「守る」ことが中心だった障がい福祉が、今では「ともに生きる」ための制度へと進化しているのです。
昔と今の制度の違いを整理
保護から共生への大きな流れ
歴史を振り返ると、障がい福祉制度は「保護と隔離」から「自立と地域生活」へ、そして「共生社会の実現」へと大きく方向転換してきました。制度は時代の価値観を映す鏡でもあり、障がい者運動や国際的な人権の潮流によって形作られてきたことがわかります。
今後の展望
今後は、誰もが地域で安心して暮らせるよう、さらなるサービスの充実やバリアフリー化が進められるでしょう。また、高齢化や多様なニーズに対応するための制度の柔軟性が求められています。