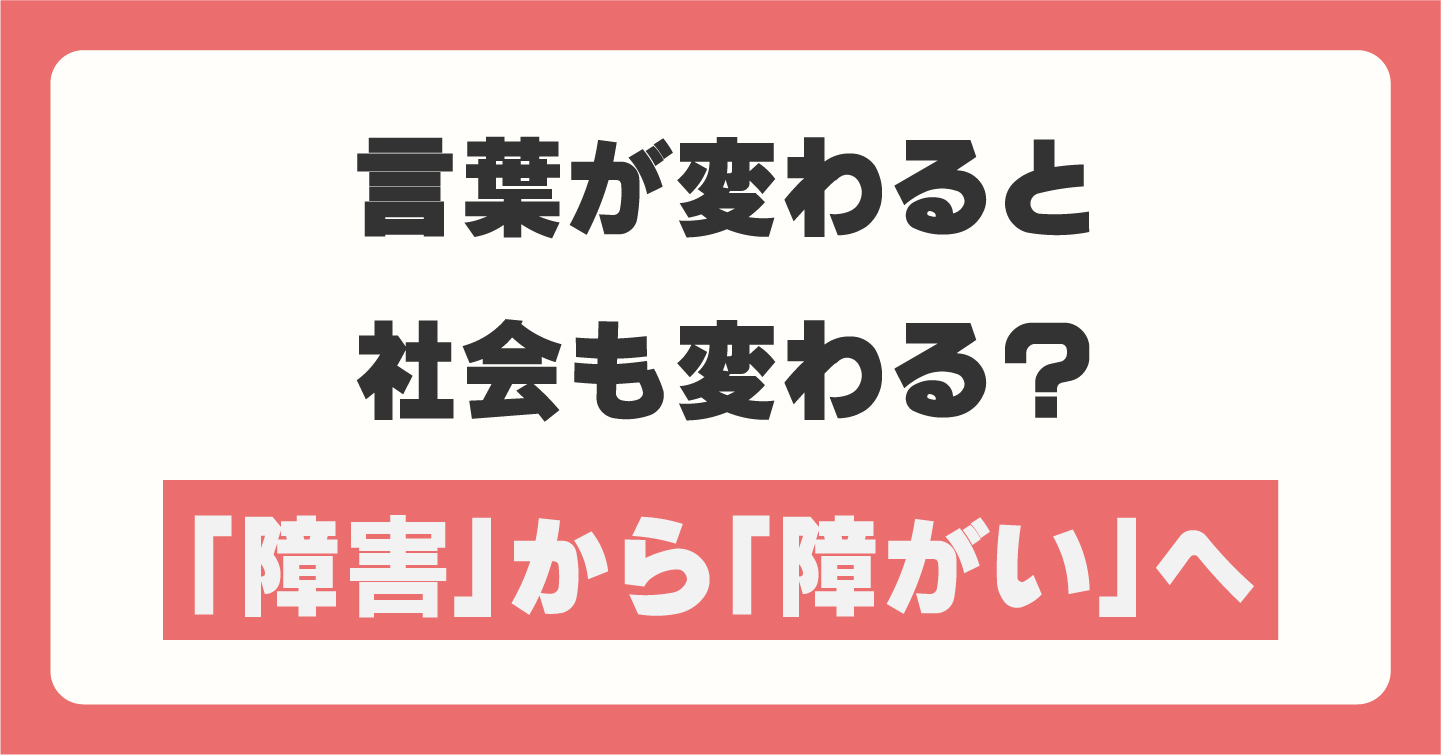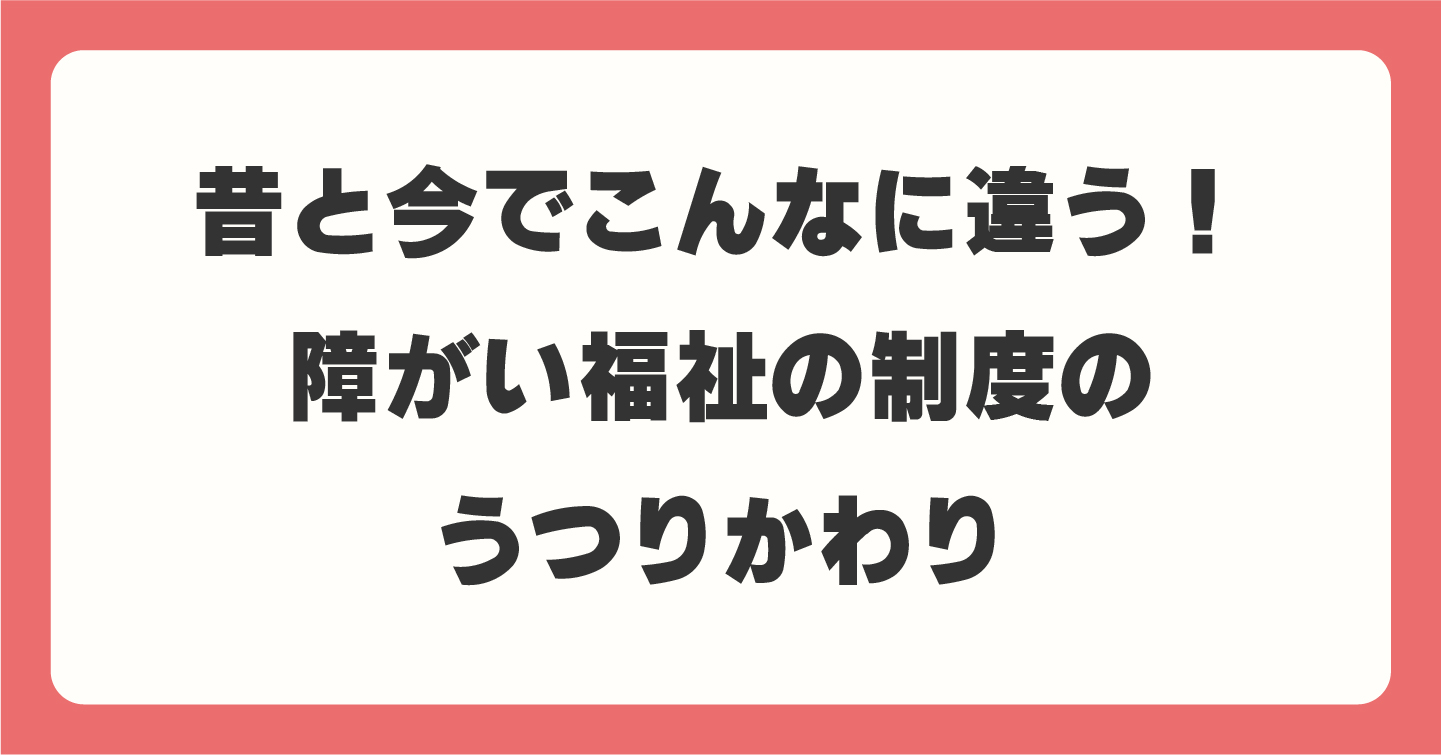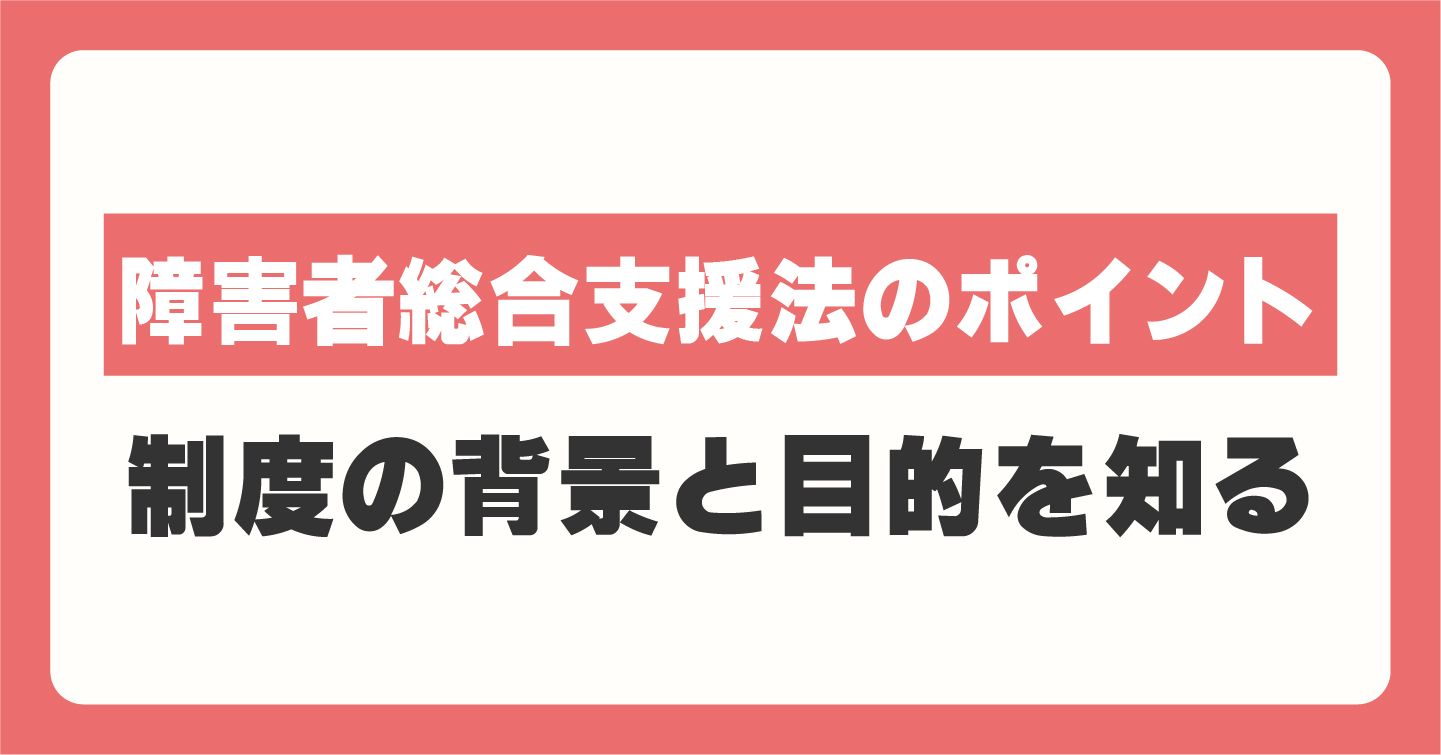日本における障がい福祉の分野では、近年「障害」という漢字表記に代わり「障がい」という表記が使われるようになってきました。この変化は単なる言葉遣いの違いではなく、社会が障がいのある人々をどう捉えるか、また共生社会をどう実現していくかという価値観の変化を示しています。本記事では、「障害」という言葉が持つ背景と、「障がい」への表記変更の経緯や意義を解説し、言葉が社会に与える影響について考察します。
「障害」という言葉が持つ意味と背景
「障害」という表記には、「障(さわり)」と「害(そこなう)」という二つの漢字が使われています。とくに「害」という字には「害悪」「加害」といった否定的な意味が含まれており、当事者や家族から「自分たちの存在を『害』と表記するのは不適切ではないか」との声が上がってきました。
一方で、法律上の表記(例:「障害者総合支援法」や「身体障害者福祉法」など)は依然として「障害」となっており、制度の正式名称としては統一されています。つまり「障害」という言葉は、行政文書や法令上の正確さを保つために使用され続ける一方、日常的な場面では「障がい」という柔らかい表記が広がりつつある状況です。
「障がい」表記が広がった経緯
2000年代以降、多くの自治体や福祉関係機関で「障がい」と表記する動きが加速しました。その背景には、当事者や市民からの「言葉による差別感情を和らげたい」という要望があります。特に2004年、文部科学省が学校教育で「障がい」という表記を用いるよう通知を出したことは、大きな転換点でした。
また、2011年に内閣府が「障がい者制度改革推進会議」の資料で「障がい」という表記を使用したことで、政府レベルでも一定の認知が進みました。これにより、行政文書の一部、パンフレット、公共機関の案内表示などで「障がい」の文字を見かけることが増えたのです。
表記の違いがもたらす社会的影響
「障害」と「障がい」は、指している対象は同じであっても、受け手の印象は大きく異なります。「害」という文字が持つ否定的な響きを避けることで、社会の中で障がいのある人々を「特別な存在」ではなく「共に生きる仲間」として受け止めやすくなるという効果が期待されています。
ただし、言葉の表記を変えるだけで差別や偏見がなくなるわけではありません。重要なのは、言葉の選び方をきっかけとして社会全体が「どう共生していくのか」を考え、行動していくことです。表記の変更は「意識の変化」を促す第一歩に過ぎないといえるでしょう。
法制度における表記の課題
現在の法律名には「障害」の表記が残されています。これは、法律が持つ安定性と統一性のため、容易に変更できない事情があるためです。法律を改正するには国会での議論や手続きが必要であり、単なる表記の問題だけでなく行政実務への影響も考慮しなければなりません。
そのため実務上は「法律名や制度名は『障害』、一般的な広報や啓発では『障がい』」という二重の使い分けが行われています。この状況については「わかりにくい」という意見もありますが、徐々に社会の理解が進むことで、将来的に統一される可能性もあります。
言葉の変化が示す共生社会への歩み
「障がい」という表記の広がりは、社会が「障害を個人の問題としてではなく、環境や社会との関係で生じるもの」と考えるようになってきた証ともいえます。これは国際的に広がる「社会モデル(障害は社会が作り出すもの)」の考え方とも一致しています。
言葉は単なる記号ではなく、社会の意識や価値観を映す鏡です。「障がい」という表記を使うことは、障がいのある人々を尊重し、多様性を受け入れる社会を築こうとする姿勢を示すものです。今後も私たちが日常生活の中で使う言葉を大切にしながら、誰もが安心して暮らせる共生社会を目指していくことが求められます。