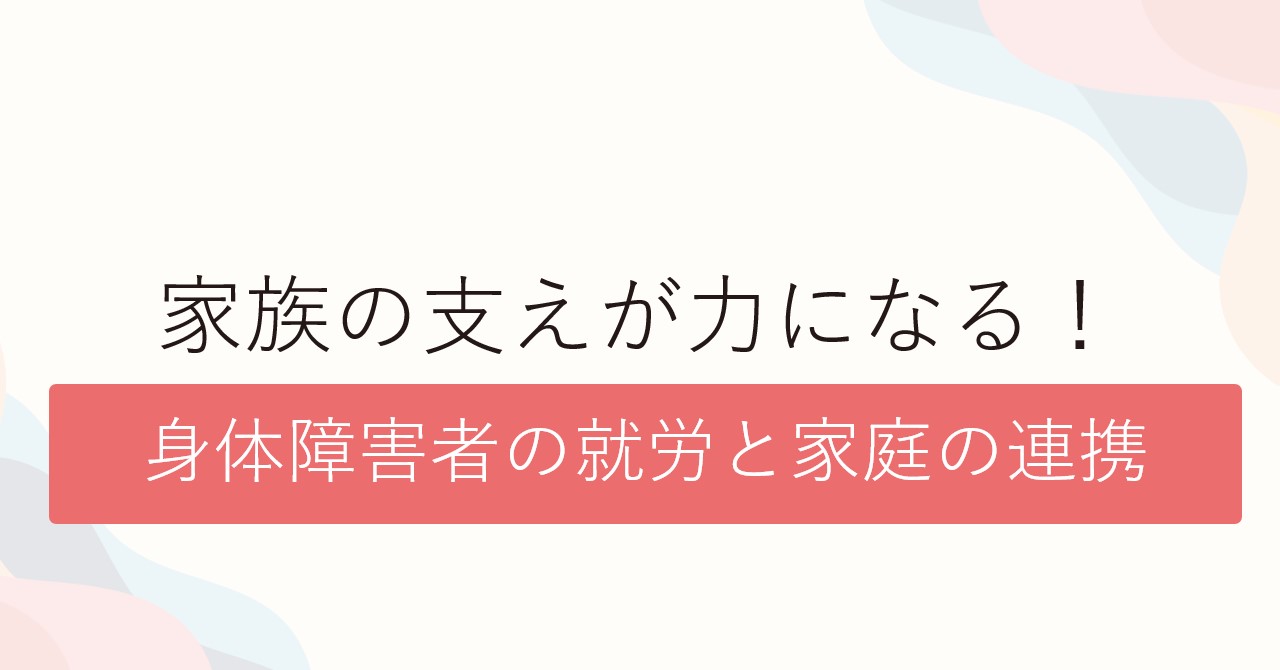身体障害のある方の就労を支えるうえで、制度や職場の配慮だけでなく、家庭・家族の役割が非常に大きくなります。家族が日常生活でどのように支えを提供するか、またどのように本人の自己決定や職業的成長を促すかによって、就労の成果や継続性が大きく変わります。本記事では、家族が果たす役割と支援のあり方について、具体的な事例・制度・課題・取り組みを交えて紹介します。家庭と制度・職場が良い形で連携を取ることが、身体障害者の就労成功につながるヒントです。
家族が面接練習や支援ツール選びに関わった例
就労のスタート時期(就職活動や採用面接など)に、家族が具体的な支えをすることで成功につなげた事例があります。例えば、ある40代の身体障害(下肢障害)を持つ方が、一般企業の事務職への就職を目指したケースです。本人は車いす使用、また通勤の移動や施設のバリアフリー化、不便を感じる点について具体的に把握していましたが、面接時にはそれを適切に伝える自己表現が苦手でした。
この時、家族が一緒に履歴書や職務経歴書の整理を手伝い、面接練習を重ねました。特に、障害特性から使いたい支援ツール(たとえば字幕付きの当日の説明資料、椅子の調整・面接会場の段差の有無など)をリストアップし、企業に事前に確認する準備をしました。また、就労移行支援事業所の見学にも家族が同行し、支援ツール・支援制度の内容を理解し、本人と共有しました。
結果として、面接の場で障害に関する配慮を遠慮なく伝えられ、通勤経路の問題や職場での机・椅子の調整なども事前に確認されました。こうした準備が採用・就労後のトラブルを減らし、職場定着率を高めることにつながりました。家族の関与が「代弁者」「準備の伴走者」として作用した例と言えます。
●家族の役割の重要性
家族は、個人の成長や社会の安定にとって非常に重要な役割を果たします。
●情緒的な支え
家族は安心感や愛情を提供し、ストレスや不安を軽減する場になります。
●社会的な教育の場
子どもは家族を通じて、社会のルールや価値観を学びます。
●経済的な支援 や介護・看護の役割
生活費の分担や、困難な時の支援など、経済的なセーフティネットとして機能します。
高齢者や病気の家族を支える役割も重要です。
●アイデンティティの形成
家族との関係を通じて、自分の価値観や人生観が形成されます。
制度・支援制度
●就労移行支援事業
身体障害者を含む障害のある方で、一般企業への就職を希望する人が利用できます。職業訓練、職場実習、生活リズムの調整などを支援します。
●就労継続支援A型・B型
一般企業での雇用が難しい場合でも、雇用契約を結ぶ(A型)か、生産活動の場を提供する(B型)などの形で働き続けるための制度です。
●障害者就業・生活支援センター
就業と日常生活の両面をサポートするセンターで、職業相談、定着支援などを行っています。家族も相談に参加可能な場合があります。
●地方自治体の就労支援センター
横浜市のように「障害者就労支援センター」を設けており、相談・適性把握・実習・フォローアップまでを家族・支援者も関わって支援する体制があります。
参考サイト:「横浜市障害者就労支援センター」
参考サイト:「厚生労働省 障害福祉サービスについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
家族と社会の協働による取り組み
●家族支援プログラム・相談窓口の整備
自治体が家族向けの相談窓口(例:家族支援相談、家族研修)を設けること。行政・福祉事業者が「家族のケア」も視野に入れた支援設計をすること。
家族だけで支えるのではなく、社会との協働を意識した取り組みが重要です。
●家族向け教育・研修
障害特性・支援ツール・コミュニケーションの工夫、法律・制度の知識など、家族が学べる場を提供する。これによって家族の不安感が軽減し、本人支援がより的確になることがあります。
●家族ネットワーク・家族会の活用
同じような経験を持つ家族同士で情報交換することで、支援アイデア・改善例を共有できます。孤立を防ぎ、励まし合いが生まれます。
●政策設計に家族の声を反映
自治体・国の制度を設計する際、家族の実際の経験を聞き取り、制度の使いにくさを改善すること。例えば、家族が仕事とケアの両立をするための時間的配慮など。
まとめ
家庭からの支えが力になるために
家族は、単に「世話をする/支える」存在ではなく、身体障害者の就労を成功させるための 伴走者・ 調整者・ 応援者 としての役割を担います。日常の生活面・感情面での支え、面接など具体的な場面での準備、制度利用のアドバイスなど、家庭でできることは多様です。
しかし、家族だけに過度な負担がかかることや、本人の自主性を奪うことにならないよう注意も必要です。社会・制度・支援機関と家庭が良く連携し、情報共有や役割分担を行うことで、持続可能で成果の出る支援が実現できます。
注意事項
※本記事の内容は、公的情報および事例を基に執筆しており、無断転載を禁止します。ご了承下さい。