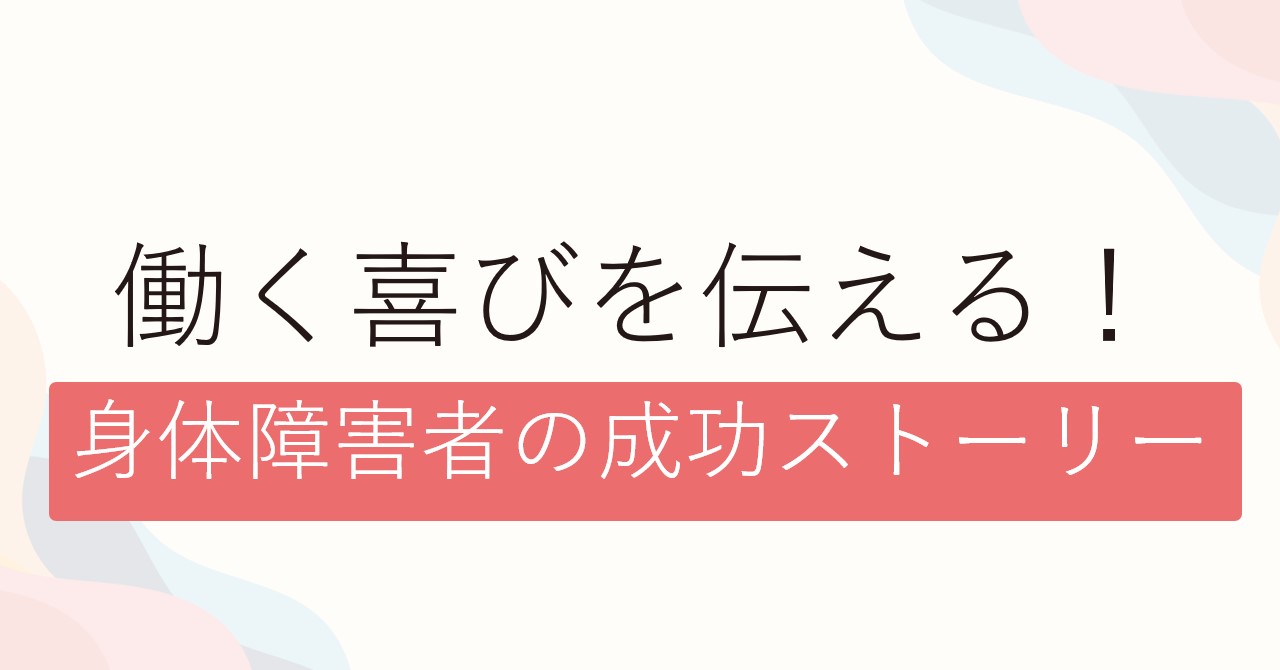身体に障害があっても「働きたい」という気持ちは誰にもあります。近年、日本では身体障害を持つ人々が就労移行支援や合理的配慮(障害特性に合わせて職場環境や働き方を調整すること)を活用し、一般企業で活躍する事例が増えています。本記事では、身体障害と労働をテーマに、実際に就労を実現した方の体験談を紹介しながら、制度・課題・取り組みを整理し、働く喜びを実感するためのヒントを探ります。
1.成功ストーリー:身体障害者の就労体験
●聴覚障害を乗り越えて事務職に就いたBさん
Bさん(30代・女性)は生まれつき聴覚障害があり、就職活動では電話応対など聴覚を要する業務に不安を抱えていました。就労移行支援事業所を利用し、自分の障害特性や希望を整理し、メールやチャット中心の業務に強みを持てることに気づきました。面接時に補聴器使用や筆談・チャットを合理的配慮として要望し、その環境を整えてくれる企業に就職。現在は同僚と協力し、チャットで確認するなど工夫しながら業務を続けています。「自分を理解してくれる職場で働けること」が、
Bさんにとって大きな喜びになっています。
●車椅子生活から在宅勤務を実現したCさん
Cさん(40代・男性)は事故で下半身にまひが残り、通勤の負担が大きく就職を諦めかけました。就労移行支援のスタッフと相談し、在宅勤務を視野に職業訓練やPCスキルを習得。現在は在宅でデータ入力や顧客対応を担当しています。「移動の負担が減り、体調管理もしやすくなった」と話し、安定して働けるようになりました。
2.支援制度と環境:利用できる制度と制度活用例
●就労移行支援とは何か?
障害者総合支援法に基づく制度で、身体障害を含む障害を持つ方が一般就労を目指すために、ビジネスマナー、職業訓練、体調管理、応募書類作成、面接練習など幅広い支援を受けられます。利用期間は原則2年。厚生労働省の調査では、就労移行支援を経て多くの人が一般企業へ移行しています。
●身体障害者雇用促進法と法定雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、一定規模の企業に法定雇用率(令和6年現在2.5%)が義務付けられています。企業は合理的配慮を提供する義務があり、設備・勤務時間・情報伝達などの調整が行われています。
参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html
●定着支援・ジョブコーチ等のサポート
就職後に継続して働けるよう、ジョブコーチ(職場適応援助者)が職場での業務・人間関係・通院調整などを支援します。本人と職場双方をつなぎ、環境調整を行うことで離職防止につながります。
● ジョブコーチ制度の活用
厚生労働省が推進するジョブコーチ制度では、専門の支援員が職場に入り、本人と企業の双方を支援します。これにより、業務上の課題や人間関係の調整がスムーズになり、差別的扱いの予防にもつながります。事例として、ジョブコーチが配置された職場では定着率が向上したとの報告もあります。
(参考:厚生労働省「障害者職業生活相談員・ジョブコーチ」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.html
3.働き続けるための課題と解決策
●定着率の現状と離職の要因
就職後3か月の定着率は約78%、1年後は60%程度と報告されており、継続が大きな課題です。通勤負担や業務量、職場の理解不足、治療との両立が離職要因に挙げられます。
●職場環境・合理的配慮の実際の落とし穴
法律で合理的配慮が求められていますが、設備や情報伝達、休憩時間の取り方など現場の調整が不十分なケースがあります。採用前に必要な配慮を確認し、職場と本人が協力して改善することが重要です。
●自己理解・障害開示のタイミング
障害特性・体調の波・得意不得意を本人が理解しておくことが、合理的配慮を企業にお願いする基盤になります。開示の方法やタイミングを支援員と相談して準備することが成功につながります。
4.新しい可能性:技術・働き方・社会意識の変化
●在宅勤務・テレワークの拡大
コロナ禍をきっかけにテレワークが一般化し、身体障害者にとって通勤負担軽減や体調管理の柔軟性など大きな利点があります。就労移行支援の中でもオンライン訓練を導入する事業所が増えています。
●ロボット・アバターロボットの活用事例
外出が難しい方が、遠隔操作型ロボット「OriHime-D」を使い接客などを行う「アバターワーク」の実証実験も進められています。障害特性に応じた新しい働き方の可能性です。
●社会の意識変化と企業事例
法定雇用率引き上げや認定制度など、制度と企業意識の両面で変化が起きています。東京都など自治体がまとめた好事例集も公開され、模範的な取り組みが広がっています。
【まとめ:働く喜びを伝えるためにできること】
身体障害があっても、自己理解・支援制度・職場との対話・技術の活用を組み合わせることで多くの方が働く喜びを実感しています。制度・企業・社会が協力し、多様な働き方や合理的配慮を整備することが、共生社会の実現への道です。
【信頼できる外部情報リンク】
厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html
厚生労働省「就労移行支援・就労定着支援 事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000527671.pdf
【無断転載不可】
本記事の内容の無断転載・転用を固く禁じます。