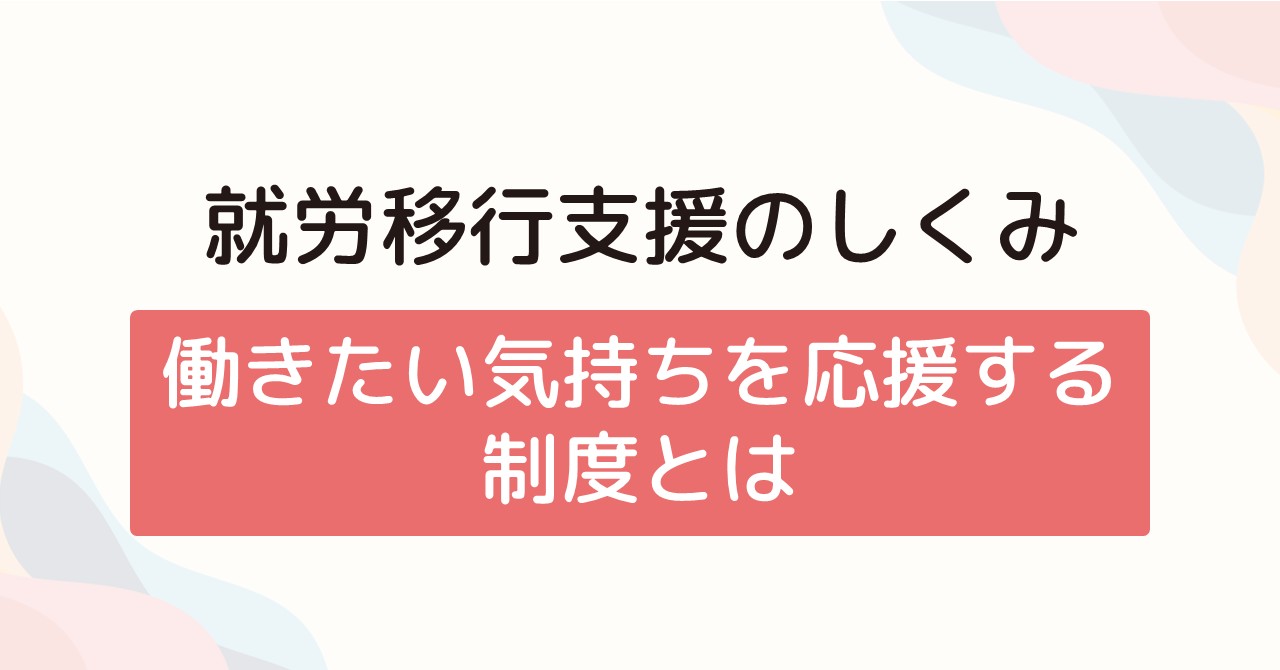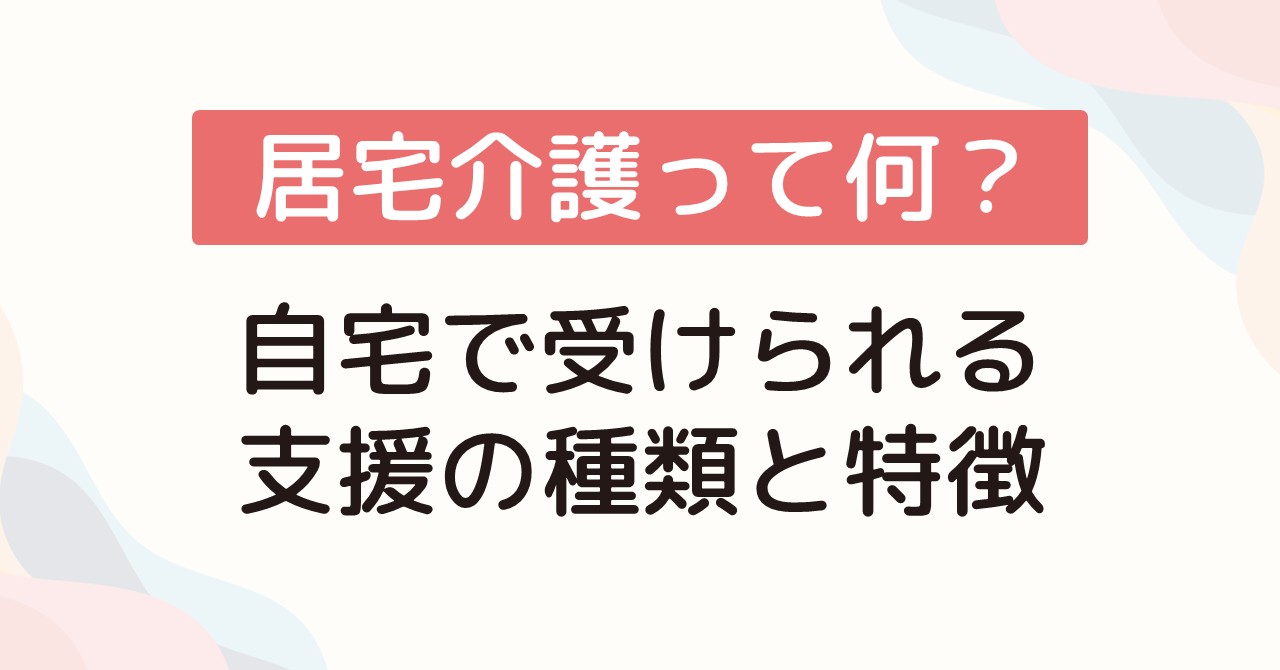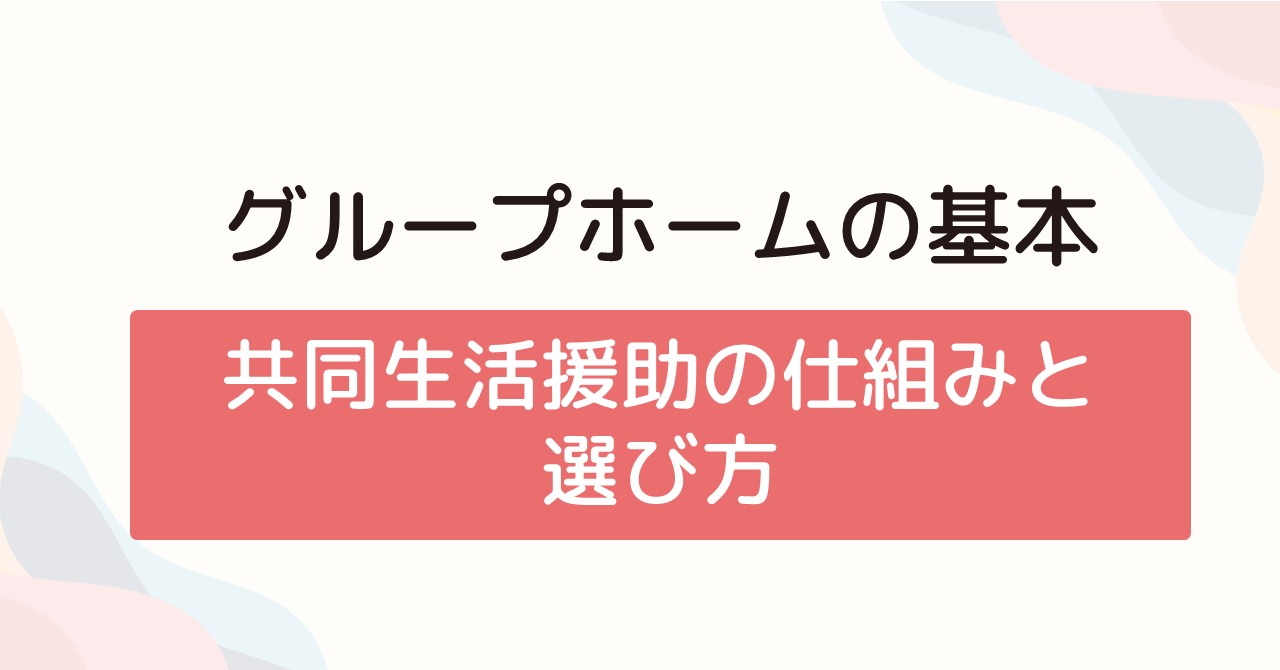障害のある方が「働きたい」と思った時、その気持ちを支える制度があります。その中でも「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す障害者に対して、必要なスキルや知識の習得・就職活動の支援、そして就職後の定着までを一貫してサポートする福祉サービスです。
本記事では基本情報や制度の流れ、関連する支援制度を紹介しながら、障害者の一般就労を支える制度について解説します。
1. 就労移行支援とは何か
就労移行支援の目的と対象者
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、一般企業への就職を希望する障害者に対して、職業訓練や就職活動の支援を行う制度です。対象は原則18歳以上65歳未満で、精神障害、発達障害、身体障害、知的障害、難病などを持つ方が含まれます。
提供される主な支援内容
- 職業能力評価とアセスメント(本人の特性や課題を把握する為の評価・分析)
- 「どんな仕事が向いているか」「どんな支援が必要か」を知る為に職業能力のチェックを行います。簡単な作業を通して集中力や作業スピードを確認したり、支援員との面談で過去の職歴や自身の得意・不得意を話しながら整理したりします。
- 社会人基礎スキルの習得職場で働く上で必要な基本的なスキルを身につけていきます。一例として、時間管理の練習の為タイマーを使って作業時間を意識する訓練を行ったり、名刺交換やビジネスマナーの講座などを実施したりします。
- コミュニケーションの訓練
- 他者と関わる力を高める為の訓練です。職場での人間関係や対人ストレスに対応する力を養います。
- 具体例:
- 他人の意見を聞く・自分の意見を伝える練習をする話し合いの後に「よかった点・改善点」をフィードバックし合うSST(ソーシャルスキルトレーニング/相手に対する振る舞いや話し方など、他者とより上手く関わっていく為に必要なスキルを練習する方法)
- 電話応対の練習(声のトーンや言葉遣いを学び、支援員と模擬演習を行う)
- 専門的な職業訓練
- 希望する職種、あるいは興味のある職種に応じたスキルを身につけるための訓練を行います。内容は事務所によって異なります。
- 具体例:
- タイピング練習、PowerPointでのプレゼン資料作成
- 書類整理などのやり方、データ入力
- 就職活動支援
- 実際の就職活動に向けた準備をサポートします。就職活動では「自分の特性をどう伝えるか」が重要であり、その為の準備を行います。
- 具体例:
- 履歴書・職務経歴書の書き方講座
- 模擬面接(支援員が面接官役になり、質問練習を行う)
- 求人票の読み方、ハローワークの利用方法、応募書類の提出方法の説明
- 面接時の服装やマナーの確認
- 職場体験・インターンシップ
- 多くの事業所では、実際の職場での短時間の就業体験やインターンシップの機会を提供しています。これにより、実際の仕事の流れや職場の雰囲気を事前に体験することができます。職場体験を経験することで、実際の就労をよりイメージしやすくなります。
- 具体例:
- 協力企業での短期間の職場体験(事務補助、清掃、軽作業など)を行う
- 支援員が同行して職場での様子を観察・記録し、後日それを利用者の方にフィードバックする
- 体験後に「何ができたか」「どこが難しかったか」を振り返る
- 就職後の定着支援
- 就職した後も、6か月の間はその職場で安定して働き続けられるように支援が続きます。
- 具体例:
- 月1回の面談で、職場での悩みを相談
- 必要に応じて職場訪問し、企業側と調整(業務内容の見直しなど)
2. 支援の流れと利用方法
利用開始までのステップ
就労移行支援を利用するには、以下のステップを踏む必要があります。
1. 障害福祉サービス受給者証と医療機関での診断・相談について
就労移行支援は障害福祉サービスの一つである為、利用するには「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」が必要です。
受給者証は、自治体がその人に対して福祉サービスの利用を認める「証明書」であり、障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用する為の「利用資格証」でもあります。
受給者証を自治体に発行してもらうには、障害や疾患の状態を証明する書類が必要です。そのため、まずは精神科・心療内科などを受診して、診断書や意見書を発行してもらう必要があります。
→ 医師に自身の障害の状況や就労に関する困難さについて相談し、「就労移行支援を利用したい」と伝えると作成してもらえることが多いです。
2. 支援事業所の見学・体験利用
通える範囲内の支援事業所を探し、気になる事業所があれば見学が可能です。見学は無料で、家族や支援者とも一緒に参加できます。通所時間や曜日、訓練内容の柔軟性も確認しておくと安心です。迷った場合は、自治体の障害福祉課窓口の相談員やハローワーク、主治医などに相談することもできます。
3. 受給者証の申請、サービス等利用計画の作成
市区町村の福祉課で相談予約を行い、面談時に必要書類を提出することで受給者証を申請します。これが発行されることで、自治体は「この人は支援が必要であり、制度の対象者である」と認定したことになります。審査・決定には通常2~4週間ほどかかります。
必要書類:
– 障害者手帳(身体・精神・療育)※なくても可
– 医師の診断書または意見書
– 自立支援医療受給者証(精神科通院中の方など)
この申請と並行して「サービス等利用計画書」も作成します。これは、どのような支援をどのような目的で受けるかをまとめた計画書です。
相談支援事業所の相談員がヒアリングを行い、計画書を作成する方法もありますが、自治体によっては自分で作成する「セルフプラン」も可能です。
また、障害者手帳と受給者証は別のものです。もし利用を検討している人が障害者手帳のみを持っていたとしても、受給者証がないと就労移行支援は受けられません。
4. 利用契約と個別支援計画の作成
受給者証が交付されたら、選んだ事業所と正式に契約を結びます。その後、事業所の支援員が「個別支援計画」を作成し、利用者の目標や課題に合わせた支援がスタートします。
5. 通所開始と職業訓練
契約後、いよいよ通所が始まります。週何回通うか、どのような訓練を受けるかは、個別支援計画に基づいて調整されます。支援員と相談しながら、無理のないペースで進めていきます。
利用期間と費用
利用期間は原則2年間で、状況に応じて最大1年間の延長が可能です。利用料は所得に応じて異なり、多くの方が無料または低額で利用できます。
3. 他制度との違い
就労継続支援との違い
就労移行支援は、一般企業への就職(=一般就労)を目指す障害者のための支援制度です。一方、就労継続支援(A型・B型)は一般就労がすぐには難しい方に対して、福祉的な環境で働く機会を提供する制度です。A型は雇用契約を結び、B型は非雇用型で作業を行います。
外部信頼リンク
厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html
あしたラボラトリー「就労移行支援とは?」
https://ashita-labo.jp/column/welfare/207/
就労選択支援ドットコム「就労選択支援に関する情報」
https://sentakushien.com/municipality/
注意事項
※本記事の内容は、厚生労働省などの公式情報をもとに執筆しています。無断転載はご遠慮ください。
※特定の団体・個人への批判的な表現は含まれておりません。